FXのチャート分析の基本的な考え方として、値動きが圧縮された後にブレイクした方向にトレンドが発生するというのがあります
三角保合いやボリンジャーバンドのスクイーズ→エクスパンジョンで判断するという方法がよく知られていますが、僕が最初に圧縮→ブレイクを意識し始めたのはボブボルマンさんのFXスキャルピングを読んでからでした
この記事では、FXスキャルピングに書いてあった手法と僕がその手法をどう解釈して使っているかを紹介していきます
この本では少し特殊なティックチャートを使っていたり、ごく短期にトレードを繰り返すスキャルピングの手法としての紹介をしていますが、プライスアクションに対する考え方はどのトレードにも通じるところがあるのでこれからチャート分析を勉強する人は株トレーダーもFXの長期トレーダーも読んでみてほしいです
ボブ・ボルマンのプライアクションを使った分析

FXスキャルピングで紹介している手法で使うインジケーターは指数移動平均線1つだけです
ただ、それ以上に特徴があるのがチャートです
最大の特徴 ティックチャート
ボブ・ボルマンさんの手法では一般的な一定時間がたつと完成するローソク足ではなくティック数で完成するローソク足を使います
ティック数とは取引きが成立した回数のことです
一般的なローソク足は5分足なら5分間の間の値動きを1本のローソク足で表します
一方ティックチャートでは設定したティック数分取引が成立するとローソク足1本が完成します
ボブ・ボルマンさんの手法では70ティックチャートを使うので70回取引きが成立すると1本ローソク足が完成します
取引が活発なら短時間で1本完成するし、取引が少なければなかなか1本完成しません
ティック70回分で1つのローソク足になるのでこの特徴を生かして、こんなふうに相場を読み取ることができます
- 70ティックのローソク足1本で60秒以上かかった場合、相場はかなり変化に乏しい
- 70ティックのローソク足1本で30秒以上かかった場合、スキャルピングしやすい地合い
- 70ティックのローソク足1本で20秒以上かかった場合、だいぶスキャルピングがイージー
70ティックチャートのデメリットは、FX業者が限定されること
70ティックチャートを使うには1つ大きな問題点があります
FX業者が限られていることです
僕はOANDA+MT4で使ったことしかありませんが、自分が使っている業者が対応していないか、各ツールの使いやすさ、スプレッドなどを比較して選んでみるといいと思います
ボブ・ボルマン氏が利用している70ティックチャート「ProRealTime」(有料)
英語表記で日本語対応はありません
月額45.19ドルで使えます
IG証券(有料)
日本語版の「IT-Finance」のチャート(ProRealTimeと同じもの)を使えます
70ティックチャートの取り扱いがある国内FX業者の独自チャート
マネックス証券(無料)
インヴァスト証券(無料)
マネーパートナーズ証券(無料)
セントラル短資(有料)
70ティックチャートをMT4で利用できるFX業者
OANDA
JFX
ティックチャートと時間足の違い

時間足では、ただ取引が少なくレートが動かないときでも、取引が活発だけど買いと売りが拮抗していてレートが動かないときも同じようなチャートを描きます
一方でティックチャートの場合、取引が少なくレートが動かないときはローソク足が完成しないので同じレートにとどまるローソク足の本数は少なくなります
また、取引が活発なのに買いと売りが拮抗しているときは、ローソク足の本数がどんどん増えていきます
こういう違いを表現してくれるのがティックチャートのいいところです
7つのセットアップ

エントリータイミングとして以下の7つのセットアップと呼ばれるプライスアクションのパターンを上げています
ダブル同時線ブレイク
ファーストブレイク
セカンドブレイク
ブロックブレイク
レンジブレイク
インサイドレンジブレイク
アドバンストレンジブレイク
これらのセットアップの多くに共通しているのが圧縮→ブレイクのプライスアクションです
ダブル同時線ブレイクでは売り買いが拮抗してレートが動かないときにあらわれる同時線が2つ現れた後にブレイクした方向にのっかるという方法をとります
またレンジブレイク、ブロックブレイクでは抵抗線にむかって移動平均線が推移していき、その間に挟まれたローソク足がどんどん値幅が小さくなっていきます
最終的に抵抗線をブレイクしたらその方向にのっかります
これらの手法から僕はFXチャートの特徴の圧縮→ブレイクの形を学びました
時間足チャートでもボブボルマンの手法は使えるか?

ボブ・ボルマンさんの手法はティックチャートを使っていますが僕は普段時間足のチャートを使っています
なので、同時線とかプライスアクションの意味はティックチャートと完全に一緒ではありません
ですが、基本的な考え方は変わりません
上昇トレンドの途中でしばらくレートが停滞するときがあります
小さいレンジ相場みたいになります
このレンジの幅が少しずつ小さくなり、上方向にブレイクするということがよくあります
チャートパターンは違っても基本的な考え方は同じなので参考になると思います
チャート分析だけでなく資金管理の考え方とかも書いてあるので、もっと詳しくセットアップの分析を知りたい人、これからトレードを始める人にはぜひ読んでほしいです
ボブ・ボルマン氏とは?
ボブ・ボルマン氏は1961年生まれで、自己資金のみでトレードを行う独立系のトレーダーです
ボルマン氏は、この記事で紹介した『FXスキャルピング ―ティックチャートを駆使したプライスアクショントレード入門』(2012)ともう1冊(僕は読んだことありません)『FX 5分足スキャルピング ―プライスアクションの基本と原則』(2015)の2冊の書籍を出版しています
ボルマン氏のプロフィールや資産は非公開ですが、インターネット上ではそのトレードの手法が高評価を得ており、世界中で安定的な人気を誇っていることが分かります
インターネット上には、ボルマン氏のスキャルピングの手法では勝てない、という否定的な意見もありますが、FXのおすすめ本として色んなサイトで紹介されており、トレード技術の独創性や実用性も含めて、ボブ・ボルマン理論は世界中のトレーダーたちに多大な影響を与えているといえるでしょう



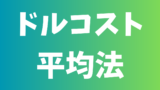
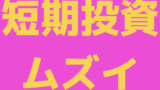



コメント