ストキャスティクスを使ってスキャルピングをやってみて1週間
今のところかなりの高勝率でトレードできていますが、全勝というわけではありません
しかもこの手法の特性上、予想が外れたときは放っておくと大きく負ける可能性が高いです
実際に損切りすることになった場面を紹介しながら、損失を少なくする方法を考えていきたいと思います
トレード前提
他の記事で紹介しているストキャスティクスを使った手法で1週間トレードしてみました
概要はこんなかんじ
通貨ペア:ユーロドル
時間足:5分足
ストキャスティクス設定:%Kの期間=5
判断ライン:%K=80以上で売り、%K=20以下で買い
取引量:1000~数万通貨
単純移動平均線(トレンド判断用):短期5期間、中期25期間、長期75期間
いくつか危ない場面があったので振り返っていきます
失敗例①

売買方向:ロング
平均エントリー/決済レート:1.0959 / 1.0949
損失幅:10 pips
エントリー理由:%K=20にタッチ
ルール通り、%Kが20にふれたところからエントリーしていきました
その後、何回かにわけてだいたい3pipsくらいレートが下がるごとにナンピンしていきました
今思えばこの時点で移動平均線が下を向いていてすでに中期移動平均線より短期移動平均線が下にあるという下降トレンドの傾向がチャートに出ていました
なのでポジションを小さめにする、ナンピンを控えるなどの対応が必要でした
一時は最初のエントリーから30pipsくらい下降するなどかなりひやひやしましたが、運よくレートが少し戻りました
損失0まで粘りたいという気持ちもありましたが、ストキャスティクスが本来ショートエントリーするラインまで来たのでポジションを決済しました
エントリー時のトレンドを意識してポジション量をコントロールする
失敗例➁

売買方向:ショート
エントリー/決済レート:1.08952 / 1.09104
損失幅:5.2 pips
エントリー理由:下降トレンド+ストキャスティクスが80に近づいてきたから
ここまで下降トレンドで来ていたのでロングはポジション小さめ、ショートは大きめでトレードしていました
トレンド発生中は、%Kが20や80の判定ラインまで届かずトレンド方向に推移していくこともあるため、少し早めにエントリーしていました
その後、3,4pipsプラスのときもあったんですがトレンド方向の売買だからと思って、少し欲張ってしまいました
その後、レートは上昇
%Kが80を超えましたが、ここが本来のエントリーポイントなのでまだ損切りはしませんでした
他の局面ならナンピンすることもある場面ですが、移動平均線が少し上向きになっていたので様子見でポジションは増やしませんでした
結局その後も上昇を続け、短期の移動平均線が中期の移動平均線を下から上に跨いだので損切りしました
損失は5pipsなのでそこまで大きい損失ではないのですが、移動平均線がクロスした時点で損切りしてもよかったかなと思いました
トレンド転換の兆しが少しでも見えたらいったん逃げる
鬼門はトレンド発生、トレンド転換
ストキャスティクスは買われすぎ、売られすぎを表すインジケーターなのでどちらかというと逆張り気味なエントリーになります
レンジ相場ならうまくサインがでたあたりで反発してくれますが、トレンドが発生、転換すると反発すると思ったところで反発せず、そのまま行ってしまいます
なので基本はストキャスティクスが判断基準といってもトレンドがどの方向に向かっているのかというのも意識しながらのトレードが大事になりそうです
ストキャスティクスを使ったスキャルピングのよくある質問
ストキャスティクスはどの時間足で使うのが効果的?
短期トレードでは5分足や15分足、中期では1時間足や4時間足などがよく使われます。
時間足が短いほどサインの頻度が増えますが、ダマシも多くなるため、トレードスタイルに合わせて選ぶことが重要です。
ストキャスティクスの設定値は何が最適?
一般的には「%K=14、%D=3、Slow=3」が標準設定ですが、スキャルピングでは「5,3,3」、スイングでは「21,9,9」など、期間を変えることで感度を調整します。
ストキャスティクスだけでエントリーしても大丈夫?
ストキャスティクス単体ではダマシが多いため、移動平均線やトレンドラインなど他のテクニカル指標と組み合わせて判断するのがおすすめです。
「%K」と「%D」のクロスはどちらを優先すべき?
%Kが%Dを下から上に抜けるゴールデンクロスで買い、上から下に抜けるデッドクロスで売りを示します。
短期線(%K)の動きを優先しつつ、トレンド方向と一致しているかを確認しましょう。
レンジ相場とトレンド相場では使い方が違う?
レンジ相場ではストキャスティクスが機能しやすい一方、強いトレンド中ではオシレーターが長期間「買われすぎ」「売られすぎ」状態を維持することがあります。
そのためトレンド中は逆張りより押し目・戻り目狙いに活用します。
ストキャスティクスの「80以上」や「20以下」は絶対基準?
あくまで目安であり、相場によっては75~85や15~25など柔軟に設定することもあります。
市場のボラティリティに合わせて調整するのが効果的です。
ストキャスティクスでダイバージェンスは活用できますか?
価格が高値を更新しているのにストキャスティクスが下がる「弱気ダイバージェンス」や、その逆の「強気ダイバージェンス」は転換サインとして有効です。
ただし他の指標と組み合わせて確認しましょう。
エントリータイミングを見極めるコツは?
ゴールデンクロス・デッドクロスの発生だけでなく、ローソク足の形やサポート・レジスタンスラインとの位置関係を確認することで、より精度の高いエントリーが可能になります。
ストキャスティクスのバックテストを行うべき?
過去データで検証することで、設定値や時間足の適性を把握できます。
取引ルールを明確化するうえでも、バックテストは非常に有効です。
ストキャスティクスのサインが頻繁に出る場合の対処法は?
期間を長く設定する、Slowの値を大きくする、上位時間足でフィルターをかけるなどの方法でサインを減らし、より信頼性の高いトレードができます。

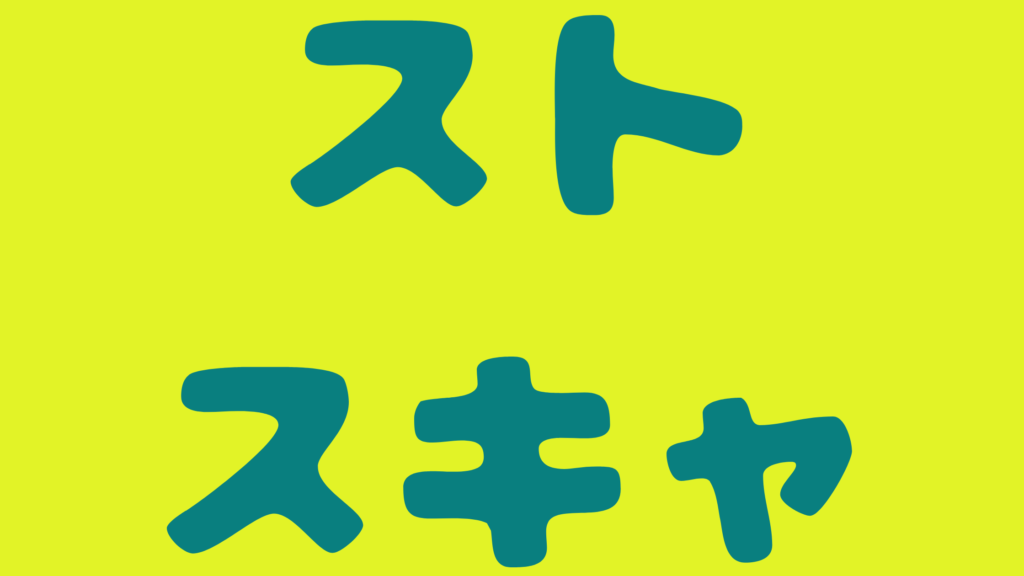
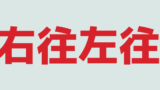

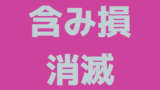
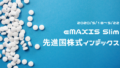

コメント