
最近もってる銘柄の株価が下がってきたけど、まだ大丈夫
四季報全部読んで厳選して、エントリータイミングもチャート見てばっちりのところで買ったし絶対上がるはず
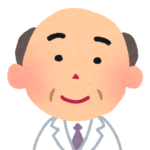
ある程度、自分の分析を信じて少しの含み損に耐えることはトレードをするうえで必要ですが、常に冷静に保有している価値がある銘柄か見直すことが必要ですよ
株式投資をやっていて損切りができるようになれば勝てるようになるとかっていう話もあるくらい、損切りは難しいです
ただ損失を受け入れるだけなのになんでできないのか
なぜ、含み損が出始めたらそのまま塩漬けにしてしまう人が多いのか
理由はいろいろあると思いますが、その1つが銘柄に対して愛着みたいなものをもってしまい手放せなくなってしまうということです
この記事では、人が含み損が膨らんでも株を手放せなくなる仕組みを解説していきます
頑張って選んだ株を簡単に手放せない
株を選ぶとき、たくさんある銘柄の中から1つの銘柄を選んで買わなければいけません
その選び方はひとそれぞれですが、それなりに労力がかかります
四季報を全部読破する人、自分が基準としている指標でスクリーニングをかける人、チャートパターンで上昇のサインが出ている銘柄を探す人などなど
それだけ労力をかけて選んだ銘柄が自分が買ったとたんに下落したらどうでしょうか
ここで売れば自分が銘柄選定に賭けた労力が一瞬で無駄になってしまうという考えが頭によぎらないでしょうか
こんな風にすでに支払ってしまった費用とか労力に引きずられてしまうことをサンクコスト効果といいます
昔、飛行機の開発がうまくいかず、でもプロジェクトをやめればその開発費が無駄になるから開発を続け結局設けられなかったなんてことがあったようです
その飛行機の名前からサンクコスト効果は別名コンコルド効果ともいいます
要するに、一度選んだ銘柄にはすでにその銘柄を選ぶための労力というコストがかかっており、それを取り返すまでは決済できないという心理が働くため、ましてやお金を損する損切りには抵抗があるのです
選択支持バイアス
例えばあなたがテレビを買おうとしているとしましょう
家電量販店に行くといろんなメーカーのいろんなテレビが展示されています
プラズマや液晶、録画ができたり4Kだったり大画面だったりと選択肢はたくさんあります
安くはない買い物なのでその分悩みますが、それでも最終的には1つを選びます
選んだあとは自分の行動を合理化したいので買える範囲で最高のテレビを買ったと信じ込もうとします
何かを選択したときに本当は他の選択肢の方がよかったのではないかという気持ちになるのは不快です
選択肢が少ない方が選択後に不満が起こりにくいことがわかっており、小売業界では客に選択肢を与えすぎないよう気を付けています
それだけ選択が間違っていたと思うことは不快であり、なので人は自分の選択は正しかったと思い込もうとします
1度買った株も、銘柄選びを間違えたと思うのは不快なのです
含み損が膨らんでも押し目買いが入るだろう、とか、値が下がれば配当利回りが高くなるからある程度の水準で買い支えられるだろうとか理由をつけて自分の判断を正当化します
株を手放したくない心理に支配されないために
サンクコスト効果や選択支持バイアスに支配されないためにはどうしたらいいんでしょうか
そういうときは自分がその株を持ってない立場に立ってみるのがよいと思います
もし、自分が今からその銘柄を新規で買おうか考えている立場でチャートや業績、指標を見た時にどう思うか冷静に見直してみましょう
新規で買う人目線でも買いたいと思えるならまだ上昇の余地があるでしょう
同じ目線で今から買いに来る人がいるかもしれません
でも新規で買いたいと思わないなら潔く損切りするべきでしょう
もし自分が損切りした後に株価が上昇したとしてもそれは必要経費だと思うべきです
株を持っている/持っていないにかかわらず、今の状態から上がるのか下がるのかを冷静に見極めることがトレードには必要だと思います
投資のサンクコストのよくある質問
サンクコスト効果とは何ですか?
サンクコスト効果とは、すでに費やしたお金や時間、労力を「無駄にしたくない」という心理が働き、合理的な判断を妨げる現象のことです。
投資では、含み損を抱えた銘柄を「いつか戻る」と信じて手放せなくなる原因になります。
選択支持バイアスとは?
選択支持バイアスとは、自分が選んだ行動を正当化しようとする心理傾向のことです。
購入した銘柄が下落しても「きっと回復する」と思い込むのは、このバイアスの典型例です。
損切りをためらってしまうのはなぜですか?
損切りをためらうのは、サンクコスト効果と損失回避の心理が重なって働くためです。
損を確定させたくない気持ちが強く、合理的な判断より感情が優先されてしまいます。
含み損がある銘柄をどう見直せばいいですか?
「今から新しく買いたいと思えるか」という視点で見直すのが有効です。
もし買いたいと思えないなら、保有を続ける合理的な理由がない可能性があります。
売却後に株価が上がった場合、どう受け止めればいいですか?
売却後の値上がりは後知恵にすぎません。
結果論で後悔するよりも、その時点での情報と判断が正しかったかどうかに焦点を当てることが大切です。
感情に左右されずに取引するにはどうすればいいですか?
売買ルールを事前に明確化し、損切りラインや利確目標を設定しておくことが有効です。
また、取引記録をつけて振り返ることで、感情的な判断を抑える助けになります。
サンクコスト効果や選択支持バイアスは誰にでも起こりますか?
はい。経験豊富な投資家でも無意識に影響を受けます。特に自分で調べて選んだ銘柄ほど「手放しにくくなる」傾向があります。
長期投資の場合はこれらの心理をどう扱えばいいですか?
長期投資では「将来の成長性」や「事業の健全性」で判断することが重要です。
単なる思い入れではなく、根拠のある長期目線で保有を続けるかどうかを見極めましょう。
株以外の投資でも同じ心理は働きますか?
はい。FXや仮想通貨などでも同様の心理が働きます。
すでに投入した資金を取り戻したい気持ちが強くなると、損切りの判断を遅らせてしまうことがあります。
サンクコスト効果を克服するための具体的な方法はありますか?
売買ルールを紙やアプリに明記し、客観的な基準を作るのが効果的です。
また、定期的にポートフォリオを見直し、第三者目線で「今この銘柄を買うならどう判断するか」を考える習慣をつけましょう。
投資のサンクコストのまとめ
この記事では、投資家が保有銘柄をなかなか手放せない心理的要因として「サンクコスト効果」と「選択支持バイアス」を解説しています。
これらは、すでに費やしたコストを惜しむ気持ちや、自分の選択を正当化したいという人間の自然な心理に基づくもので、冷静な投資判断を妨げる代表的なバイアスです。
特に株式投資では、「ここまで下がったら損切りできない」「自分の判断は間違っていないはず」といった感情が強く働き、結果的に損失を拡大させてしまうケースが少なくありません。
このような心理に対抗するには、事前に売買ルールを決めておくことや、「今から新しく買いたい銘柄か?」という視点で保有株を見直すことが有効です。
また、取引を記録して振り返る習慣を持つことで、自分の判断傾向を客観的に把握できるようになります。
サンクコスト効果や選択支持バイアスを理解し、自分の感情を冷静に観察できるようになることは、長期的に安定した投資成果を上げるための第一歩といえるでしょう。

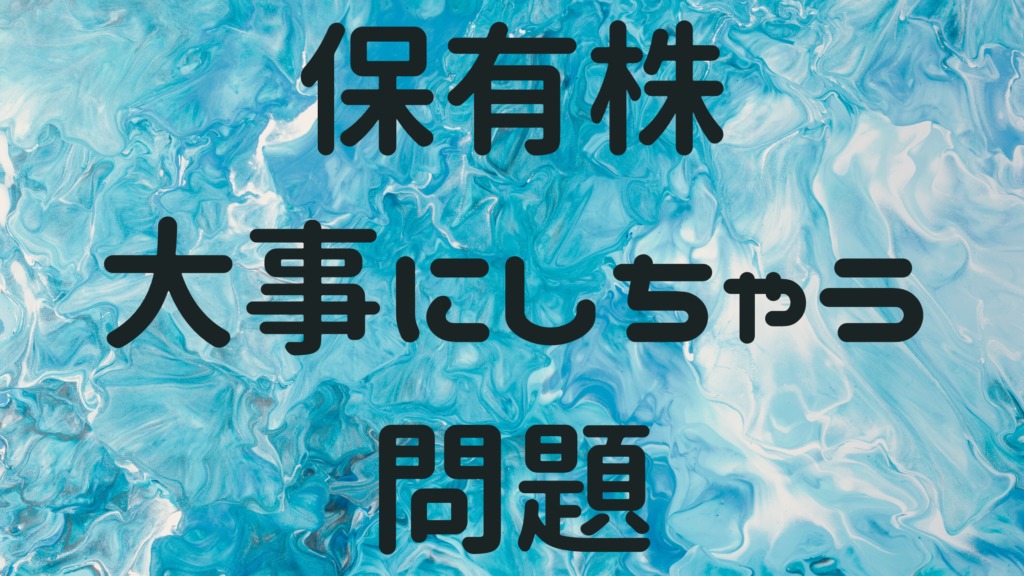
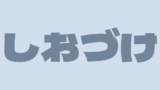
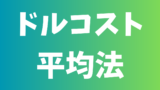
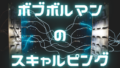

コメント