S&P500はアメリカを代表する株価指数であり、長期的には右肩上がりの成長を見せてきました。
しかし、その歴史の中では幾度となく暴落を経験しており、多くの投資家にとっては「いつ暴落するのか?」「暴落時にどう行動すべきか?」という不安がつきまといます。
本記事では、S&P500の暴落の歴史を代表的な出来事とともに振り返り、なぜ暴落が起こるのか、そして暴落局面でどのような投資判断や心構えが求められるのかを、初心者にもわかりやすく解説します。
歴史を学ぶことで、次の暴落に備える知識と冷静さを身につけていきましょう。
S&P500の暴落の歴史
S&P500の歴史には、世界経済を揺るがすような大規模な暴落がいくつも記録されています。
ここでは代表的な暴落事例を時系列で紹介します。
世界恐慌
世界恐慌は1929年10月にアメリカの株式市場が大暴落したことをきっかけに、世界中に広がった経済危機です。
S&P500の前身である指数は、この時期に約86%もの下落を記録し、回復までに25年を要しました。
投資家のパニック売りが連鎖し、金融機関の破綻や失業率の急上昇を招いたことが特徴で、暴落が経済全体に与える深刻な影響を象徴する出来事です。
ブラックマンデー
ブラックマンデーとは、1987年10月19日に起きた史上最大級の株価急落のことです。
この日、S&P500はわずか1日で20%以上の下落を記録しました。
原因としては、コンピュータによる自動売買(プログラム・トレーディング)の暴走や、過度な株価の過熱感、金利や為替市場の不安定さなどが挙げられます。
この暴落は短期間での下落率としては異常に大きく、現在でも市場参加者の間で語り継がれる歴史的事件です。
リーマン・ショック
リーマン・ショックは、2008年9月にアメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻したことで引き起こされた世界的金融危機です。
S&P500は2007年の高値から2009年初頭の安値までに約57%下落し、個人・法人を問わず多くの資産が大きな損失を被りました。
サブプライムローン問題を発端とした信用収縮が、世界中の金融機関に波及し、実体経済にも深刻な影響を与えたことから、現代で最も重大な暴落の一つとして記憶されています。
フラッシュクラッシュ
フラッシュクラッシュは、2010年5月6日に発生した超短時間の急落現象です。
この日、S&P500はわずか数分のうちに約9%下落し、その後すぐに大部分を回復しました。
原因は高頻度取引(HFT)やアルゴリズム取引による連鎖的な売り注文の発生とされており、市場の脆弱性が浮き彫りになった出来事です。
わずか20分足らずで数千億ドル規模の時価総額が一時的に失われたことから、金融市場の技術的リスクが強く意識されるようになりました。
OPECクラッシュ
OPECクラッシュは、2020年3月に石油輸出国機構(OPEC)とロシアの協調減産交渉が決裂したことで発生した原油価格の急落に端を発する暴落です。
原油価格の急落により、エネルギー関連株が大幅に売られ、S&P500も短期間で急落しました。
この時期は新型コロナウイルスの感染拡大とも重なり、市場の不安心理が一気に高まりました。
この出来事は、エネルギー市場と株式市場の連動性、そして地政学リスクが株価に与える影響を再認識させるきっかけとなりました。
コロナ・ショック
コロナ・ショックは、2020年2月下旬から3月にかけて世界的に株式市場が急落した現象で、新型コロナウイルスのパンデミックによる経済活動の停止が主な原因です。
S&P500はわずか1か月で約34%下落し、多くの投資家が市場の急激な変化に対応を迫られました。
しかし、前例のない規模の金融緩和や財政出動が迅速に行われたことで、その後の株価は短期間で急回復を遂げました。
この暴落は、世界の中央銀行と政府の介入が市場心理に与える影響を強く印象づけた事例でもあります。
主な暴落局面と下落率一覧
過去50年のS&P500の代表的な暴落局面と下落率を一覧でまとめます。
それぞれの背景とあわせて理解することで、暴落パターンの傾向を把握できます。
| ショック名 | 期間 | ドル建て下落率 | 円建て下落率(参考) |
|---|---|---|---|
| 第1次オイルショック | 1973年~1974年10月 | 約‑48.2% | 約‑52.9% |
| 第2次オイルショック | 1980年2月~3月 | 約‑30.1% | 約‑32.0% |
| ブラックマンデー | 1987年8月~10月 | 約‑33.2% | 約‑35.5% |
| ITバブル崩壊 | 2000年3月~10月 | 約‑49.2% | 約‑39.5% |
| リーマン・ショック | 2007年10月~2009年3月 | 約‑56.8% | 約‑63.2% |
| コロナ・ショック | 2020年2月~3月 | 約‑33.9% | 約‑27.3% |
| インフレ・金利ショック | 2022年1月~10月 | 約‑25.4% | 約‑10.2% |
このリストは、過去50年において約7〜10年ごとに40%前後の下落が起きている傾向を示し、暴落に「インフレ型」と「金融危機型」の二つのパターンがあることを裏付けています。
S&Pの暴落はなぜ起きたのか?歴史を振り返る
S&P500が暴落する背景には、単なる値動きの乱高下ではなく、経済・金融・地政学的なさまざまな要因が絡んでいます。
ここでは、歴史的暴落の共通原因を大きく3つに分けて解説します。
バブルの崩壊
S&P500の歴史において、バブル経済の崩壊はたびたび暴落の引き金となってきました。
代表的なのは2000年代初頭のITバブル崩壊です。
この時期、ハイテク株を中心とする過剰な期待と投機的資金が株価を押し上げましたが、企業の業績が追いつかず、やがて投資家の信頼が崩れ始め、S&P500は約49%もの下落に見舞われました。
バブルの特徴は、実体経済とかけ離れた過剰評価と、それに続く急激な反動です。投資家が「永遠に上がる」と思った時、崩壊は始まっています。
金融引き締め政策
金融引き締め、特に利上げや量的縮小(QT)は、株式市場にとって大きなマイナス要因となり得ます。
FRB(米連邦準備制度)がインフレ抑制のために金利を急激に引き上げた場合、企業の資金調達コストが上がり、将来の利益が目減りするとの見方から株価は下落しやすくなります。
2022年のインフレ・金利ショックでは、FRBの急速な利上げがS&P500の25%超の下落を招きました。
過去の暴落の多くで「金融引き締め」が共通要因となっており、中央銀行の政策動向には常に注意が必要です。
情勢不安・戦争
地政学リスクや戦争、政治的混乱などの情勢不安も、S&P500の暴落要因として無視できません。
たとえば、1970年代のオイルショックは中東の紛争が引き金となり、原油価格の急騰とともに世界経済を揺るがしました。
また、湾岸戦争やロシアのウクライナ侵攻なども市場の不安心理を高め、一時的な急落を引き起こしています。
このような外部要因は予測が困難であり、発生時の市場への影響は極めて大きいため、ポートフォリオの分散や備えが重要です。
S&P500の暴落の歴史から学ぶ暴落局面における資産運用の心構え
暴落はいつか必ずやってくるものですが、適切な心構えがあれば慌てずに乗り越えることができます。
ここでは、過去の暴落から導き出せる2つの重要な投資姿勢を紹介します。
群集心理に惑わされない
暴落局面では、多くの投資家がパニックに陥り、一斉に売却へと走る「群集心理(集団行動)」が市場を加速的に動かします。
その結果、実態以上に過剰な下落が起こることも珍しくありません。
しかし、歴史を振り返れば、暴落のたびに市場はやがて回復してきたことが分かります。
他人の動きに流されず、冷静な視点を持ち続けることこそ、長期投資において最も重要な心構えのひとつです。
自分のリスク許容度を再確認する
暴落が起きたときに焦って資産を売却してしまうのは、自分のリスク許容度を超えた投資をしている証拠かもしれません。
市場が順調なときには気づきにくいですが、暴落時こそ自分の「本当の耐性」が試されます。
どの程度の損失まで冷静でいられるか、どの期間まで資産を寝かせておけるかを事前に見極めておくことは、長期投資において極めて重要です。
リスク許容度に見合った投資を行うことで、暴落時にも自信を持ってポジションを保つことができます。
S&P500暴落の歴史から考えるリスク対策3選
暴落は避けられないものですが、過去の教訓をもとにリスクを抑える方法はあります。
ここでは、S&P500の暴落を踏まえて取るべき具体的な対策を3つ紹介します。
売買のタイミングを分散する
一度にまとめて投資をする「一括投資」は、暴落直前に買ってしまうリスクがあります。
これを避けるためには、買付時期を分散する「ドルコスト平均法」などの手法が有効です。
たとえば毎月一定額を積み立てることで、高値づかみのリスクを抑えつつ、価格が下がったときにはより多くの口数を購入できます。
売却のタイミングも同様に分散することで、大幅な損失や機会損失を防ぎ、心理的な負担も軽減されます。
株と値動きが連動しない資産に投資する
株式市場が暴落するとき、すべての資産が同じように下がるわけではありません。
金(ゴールド)や債券、REIT(不動産投資信託)など、株と異なる値動きをする資産を組み合わせることで、リスクの分散が可能です。
たとえば、2008年のリーマン・ショックでは株式が大きく下落した一方で、金や一部の国債は価格が上昇し、資産全体の下支えとなりました。
異なる資産クラスを組み入れることで、ポートフォリオ全体の値動きを安定させ、暴落時のダメージを和らげる効果が期待できます。
安定成長が見込める海外投資も視野に入れる
米国株中心のポートフォリオは高い成長性が期待できる一方、米国経済や金融政策の影響を大きく受けるため、集中リスクが生じます。
そのため、安定した経済成長が見込まれる新興国や、政治・経済リスクが比較的低い欧州・アジア圏への分散投資も検討の価値があります。
国・地域ごとの経済サイクルの違いを活用することで、一国の暴落にポートフォリオ全体が引きずられるリスクを軽減できます。
S&P500を中心としつつも、グローバルな視点を持つことが、より安定した資産形成につながります。
S&P500の暴落の歴史のよくある質問
S&P500は過去に何回暴落していますか?
おおよそ10回以上の大規模な暴落が記録されています。
代表的なものとしては、1929年の世界恐慌、1987年のブラックマンデー、2000年のITバブル崩壊、2008年のリーマン・ショック、2020年のコロナ・ショックなどがあり、いずれもS&P500が20%以上下落したケースです。
平均すると7~10年ごとに大きな暴落が起きており、長期投資をするうえで避けては通れない現象です。
最も大きなS&P500の暴落はいつですか?
最も大きな下落率を記録したのは1929年の世界恐慌です。
このときS&P500は約86%の下落を記録し、回復には25年を要しました。
現代における最大の暴落は2008年のリーマン・ショックで、約57%の下落が発生しました。
これらの暴落は歴史的な経済危機と密接に関係しており、投資家にとって重要な教訓となっています。
暴落中にS&P500を売るのは正解ですか?
基本的にはおすすめできません。
暴落中に売却すると、損失が確定してしまい、その後の回復相場に乗り遅れるリスクがあります。
過去の例では、S&P500は暴落後に必ず回復してきたため、長期的な視点で保有を継続するほうが合理的とされています。
ただし、自身のリスク許容度を超えている場合は、ポジションの見直しが必要です。
S&P500は暴落後どのくらいで回復しますか?
回復までの期間は暴落の規模によって異なりますが、平均して1〜5年程度です。
たとえば、リーマン・ショック後の回復には約5年、コロナ・ショックでは約半年と、回復スピードには大きな差があります。
長期投資では、このような一時的な下落に焦らず、継続的に資産を保有し続ける姿勢が重要です。
S&P500は長期保有でも損することがありますか?
十分な期間を取れば、過去にはほとんどの場合でプラスになっています。
歴史的に見ると、S&P500を15年以上保有した場合、元本割れしたケースはほとんどありません。
ただし、投資タイミングが極端に悪かった場合や、暴落後に途中で売却してしまった場合には損失を出す可能性もあります。
長期投資の基本は「時間を味方につける」ことです。
インデックス投資と暴落の関係は?
インデックス投資も暴落の影響を受けますが、長期的には回復が見込まれます。
S&P500のようなインデックスは市場全体の平均的な動きを反映するため、暴落時には下落しますが、経済成長とともに元に戻る傾向があります。
個別株と違って倒産リスクがなく、複数銘柄に分散されている点が強みです。定期的な積立と長期保有を前提とすれば、暴落はむしろ「安く買えるチャンス」と考えることもできます。
過去の暴落から何を学べますか?
最も大きな教訓は「暴落は必ず起こるが、いずれ回復する」ということです。
歴史を振り返れば、どんなに深刻な暴落でもS&P500は時間をかけて高値を更新してきました。
このことから、暴落時に慌てて売らず、事前にリスクに備えておくことの重要性がわかります。
また、暴落時は投資家心理が過度に悲観に傾きやすいため、冷静な判断力と長期視点が成功の鍵になります。
S&P500が暴落すると他の資産も下がりますか?
多くの場合、連動して下がる資産もありますが、すべてではありません。
特に株式と相関の高い資産(米国株、ハイイールド債など)は一緒に下落しやすい一方で、金(ゴールド)や米国債などは安全資産として買われる傾向があります。
ただし、リーマン・ショックのような信用不安が広がる暴落時には、一時的に「すべて売られる」現象が起こることもあり、完全な回避は困難です。
そのため、リスクの異なる資産を組み合わせておく「分散投資」が重要です。
暴落が怖いならS&P500に投資しないほうがいい?
暴落が不安でも、長期的な視点を持てるならS&P500は有力な選択肢です。
短期的な値動きに過敏に反応してしまう人には向かないかもしれませんが、過去の実績を見るとS&P500は長期保有で安定したリターンを生み出してきました。
暴落時の不安を軽減するには、積立投資や資産配分の工夫、投資金額を抑えるなど、自分に合った投資スタイルを選ぶことが大切です。
次の暴落はいつ起きると予想されていますか?
正確に予想することはできません。
市場の暴落は経済指標や地政学的リスク、金融政策など複雑な要因が絡み合って突然発生するため、事前に「いつ起きるか」を断定することは不可能です。
むしろ、いつか暴落は起きるという前提で投資を設計し、リスク分散や長期視点を持って備えることが現実的な対応策です。
S&P500の暴落の歴史のまとめ
S&P500は過去100年にわたって数々の暴落を経験してきましたが、そのたびに回復し、長期的には右肩上がりの成長を続けています。
歴史を知ることで、暴落が「例外」ではなく「前提」であることを理解し、冷静な投資判断ができるようになります。
一時的な価格の乱高下に惑わされず、自分のリスク許容度に合った資産配分と長期的な視点を持つことが、暴落に強い投資家への第一歩です。


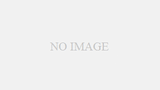
コメント