「投資信託とETFって、どう違うの?」「どちらを選べばいいの?」——これから積立投資を始めたい人にとって、最初の悩みがここかもしれません。
どちらも少額から始められて分散投資が可能な金融商品ですが、仕組みやコスト、取引方法などに違いがあります。
この記事では、初心者でも5分で理解できるように、投資信託とETFの違いをわかりやすく解説。
それぞれのメリット・デメリットを比較し、あなたに合った投資スタイルの見つけ方も紹介します。
投資信託とETFの基本を理解しよう
まずは、投資信託とETFそれぞれの基本をおさえましょう。
どちらも複数の銘柄に分散投資できる商品ですが、取引の仕組みや運用方法に違いがあります。
仕組みを理解することで、後の比較もスムーズになります。
投資信託とは
投資信託(ファンド)は、投資家から集めたお金をまとめて運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに投資する仕組みです。
1万円程度の少額から始められ、複数の銘柄に分散投資できるため、初心者にも人気があります。
通常は1日1回、基準価額と呼ばれる価格で取引され、証券会社や銀行を通じて購入します。
| 商品名 | 運用会社 | 主な投資対象 | 信託報酬(年率) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント | 世界各国の株式 | 0.1133%程度 | 全世界に分散投資できる人気ファンド |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問 | 米国株式(VTI) | 0.162%程度 | 米国市場全体に低コストで投資できる |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント | 先進国株式 | 0.1023%程度 | 信託報酬が業界最低水準でコスパ良好 |
| つみたて先進国株式 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 先進国株式 | 0.1102%程度 | つみたてNISAにも対応、長期投資向き |
ETFとは
ETF(上場投資信託)は、証券取引所に上場している投資信託の一種です。株式と同じように、取引所でリアルタイムに売買できるのが大きな特徴です。
多くのETFは「インデックス型」で、日経平均やS&P500などの指数に連動した運用を行います。
手数料が比較的安く、価格の透明性も高いため、コスト重視の投資家に支持されています。
| 商品名 | 運用会社 | 主な投資対象 | 信託報酬(年率) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信(2559) | 三菱UFJアセットマネジメント | 全世界の株式 | 0.0858%程度 | 東証に上場した全世界株ETF、日本円で取引可 |
| SPDR S&P500 ETF(1557) | ステート・ストリート | 米国S&P500 | 0.0945% | 米国を代表する大型株に投資、日本でも購入可 |
| バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT) | バンガード | 全世界株式 | 0.07% | 米国ETFの定番。1本で世界中の株式に投資可能 |
| iシェアーズ・コア 米国総合債券市場ETF(AGG) | ブラックロック | 米国債券 | 0.03% | 債券ETFとして安定志向の投資家に人気 |
共通点と基本的な仕組み
投資信託とETFは、いずれも「複数の資産にまとめて投資できる」点が共通しています。
これにより、リスクを分散しやすく、資産運用の入門として最適です。
どちらもプロによって運用されており、個別株よりも手軽に投資を始められる点も魅力です。
ただし、購入のタイミングや手数料の仕組みなど、具体的な運用方法には違いがあります。
投資信託とETFの違いを比較
投資信託とETFは、どちらも分散投資ができる便利な金融商品ですが、「どうやって買うのか」「いつの価格で買えるのか」「コストはどれくらいか」などに大きな違いがあります。
ここでは、初心者が特に気になる4つの視点から両者を比較していきましょう。
取引方法とタイミング
ETFは株式と同じように、証券取引所が開いている時間帯であればリアルタイムに売買できます。
指値注文や成行注文といった注文方法も活用可能です。
一方、投資信託は1日1回算出される「基準価額」で取引が成立します。
取引の受付は営業日中であっても、実際の価格はその日の終値ベースとなるため、購入価格がすぐにはわからないという特徴があります。
手数料とコスト
一般的にETFの方が手数料は安く、信託報酬(保有中にかかるコスト)も低めに設定されています。
ただし、売買時には取引手数料がかかる場合があります。
投資信託は購入時手数料や信託報酬がETFより高めな傾向がありますが、ノーロード(購入手数料無料)ファンドも増えており、選び方次第でコストを抑えることも可能です。
| 商品名 | 種類 | 購入手数料 | 信託報酬(年率) | 売買時の手数料 |
|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 投資信託 | 無料(ノーロード) | 0.1133%程度 | なし(販売会社により異なる) |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 投資信託 | 無料(ノーロード) | 0.162%程度 | なし(販売会社により異なる) |
| SPDR S&P500 ETF(1557) | ETF | 証券会社の取引手数料がかかる | 0.0945% | 約定代金の0.1%程度(証券会社により異なる) |
| MAXIS全世界株式(2559) | ETF | 証券会社の取引手数料がかかる | 0.0858%程度 | 約定代金の0.1%前後 |
購入場所と最低購入金額
投資信託は銀行や証券会社、ネット証券などで購入でき、1万円未満でも積立投資に対応している商品が豊富です。
一方、ETFは証券口座を通じて取引所で購入する必要があり、売買単位(通常1口または10口)によっては投資額が高くなることもあります。
とはいえ、ネット証券を使えば少額投資できるETFも多く、参入障壁は下がっています。
| 商品名 | 種類 | 最低購入金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 投資信託 | 100円~ | 積立NISA・iDeCo対応 |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 投資信託 | 100円~ | VTI連動、米国市場に分散 |
| SPDR S&P500 ETF(1557) | ETF | 約5万円~(1口単位) | 価格は為替や市況により変動 |
| MAXIS全世界株式(2559) | ETF | 約1,500円~(1口単位) | 東証上場、日本円で取引可 |
分配金と自動再投資
投資信託は多くの商品で「分配金の自動再投資」が選べるため、手間をかけずに複利効果を活用できます。
ETFは分配金が現金で支払われるのが基本で、自動再投資は原則できません。
そのため、自分で再投資の手続きをする必要がありますが、配当を自由に使えるという柔軟性もあります。
投資信託とETFのメリットとデメリットの違い
投資信託とETFには、それぞれ異なるメリットとデメリットがあります。
ここでは両者の特徴を整理し、自分に合った投資スタイルを見つけるためのヒントを紹介します。
コストの安さや使い勝手、自由度など、選ぶ際に重視したいポイントを確認してみましょう。
投資信託のメリット・デメリット
投資信託のメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット:
・少額から始められる
・積立投資に対応している商品が多く、自動化しやすい
・分配金を自動で再投資できるため、複利効果を活かしやすい
・長期投資向けの商品が豊富
デメリット:
・取引価格が1日1回の基準価額で決まり、リアルタイムの価格で売買できない
・ETFと比べて信託報酬がやや高めの商品が多い
・注文後すぐに価格が確定しないため、タイミングを読みづらい
投資信託は、手軽さと積立のしやすさを重視したい人に向いています。
ETFのメリット・デメリット
ETFのメリット・デメリットは以下の通りです。
メリット:
・株と同じようにリアルタイムで売買ができる
・信託報酬などの運用コストが比較的低い
・市場価格が可視化されており、透明性が高い
・売買の自由度が高く、指値・成行注文にも対応
デメリット:
・自動積立や分配金の自動再投資が基本的にできない
・取引には証券口座が必要で、口座開設が前提
・市場の状況によっては、価格が基準価額と乖離するリスクがある
ETFは、コストや自由度を重視する中級者以上の投資家に向いています。
投資信託とETF どちらが自分に向いているか
投資信託とETFにはそれぞれ異なる特徴があり、どちらが適しているかは投資スタイルや目的によって変わります。
ここでは、代表的なタイプ別に「向いている人の特徴」や「選び方のポイント」を具体的に見ていきましょう。
初心者や積立投資派に向いているのは?
初めての資産運用や、コツコツ積立投資をしたい人には投資信託がおすすめです。
自動積立ができ、分配金も自動再投資されるなど、長期的な資産形成に向いた仕組みが整っています。
ネット証券では100円から投資できるサービスもあり、ハードルの低さも魅力です。
結論:投資初心者や積立で資産を育てたい人には、投資信託がぴったりです。
コスト重視や能動的に売買したい人には?
取引の自由度を重視したい、またはできるだけコストを抑えて効率よく資産運用したい人にはETFが向いています。
リアルタイム売買や指値注文が可能で、信託報酬も比較的安く抑えられています。
自分でタイミングを見て売買できるので、より積極的な投資がしたい方に最適です。
結論:コストや取引の自由度を重視する人には、ETFがおすすめです。
ケース別の選び方
例えば「毎月定額でほったらかし投資をしたい人」は投資信託、「特定の指数やテーマに沿って自分で選びたい人」はETFといったように、自分の投資スタイルに合わせて使い分けることも可能です。
最近では、NISAやiDeCoなど制度に合わせた商品選びも重要な視点となっています。
結論:投資スタイルに応じて、投資信託とETFを使い分けるのも賢い選択です。
投資信託とETFの違いのよくある質問(FAQ)
投資信託とETF NISAではどちらがおすすめ?
新NISA制度では、投資信託とETFのどちらも対象となっています。
積立投資枠を活用するなら、積立設定に対応している投資信託が使いやすいでしょう。
一方で、成長投資枠ではETFも選択肢に入ります。
税制優遇を最大限活かすには、自分の投資スタイルに合った商品を選ぶのが重要です。
結論:積立メインなら投資信託、自由に売買したいならETFがNISAと相性◎です。
投資信託とETFの併用はできますか?
はい、もちろん可能です。
たとえば、毎月の積立は投資信託で行い、余剰資金でテーマ型ETFをスポット購入するという併用スタイルは、リスク分散と効率的な運用の両立に役立ちます。
最近では同じ指数に連動する投資信託とETFを両方用意している金融機関も増えています。
結論:併用することで柔軟かつ戦略的な資産運用が可能になります。
リスクはどちらが高いのか?
基本的なリスクはどちらも同じですが、「価格の動き方」に違いがあります。ETFは市場価格がリアルタイムで変動するため、相場の影響を受けやすく、短期的な値動きが気になる人にはストレスとなるかもしれません。
投資信託は基準価額での取引のため、相場変動が見えにくい一方、価格の透明性が低いという側面もあります。
結論:リスクの大きさよりも「価格の見え方」に違いがある点に注意が必要です。
投資信託とETFの違いのまとめ
ここまで、投資信託とETFの基本から違い、選び方までを見てきました。
最後に、それぞれの特徴をふまえて、あなたにとって最適な選択ができるよう、ポイントを整理しておきましょう。
・投資信託は、少額で始められ、自動積立や再投資に対応しているため、長期的にコツコツ資産を増やしたい初心者向け。
・ETFは、リアルタイム売買が可能で、信託報酬が低くコストを抑えられるため、自分でタイミングを見て運用したい人向け。
・投資スタイルや目的によって、「使い分け」や「併用」も十分に選択肢になる。
・NISA制度を活用すれば、税制面でも効率的な運用が可能になる。
投資信託とETF、どちらが正解かではなく、「自分に合った投資」を見つけることが大切です。


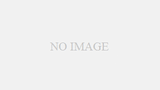
コメント