SNSやマッチングアプリを通じて接触し、甘い言葉や投資話で近づいてくる「SNS型投資詐欺」。
近年、被害額が数千万円に及ぶケースも多発し、警察や消費者庁も注意を呼びかけています。
本記事では、SNS型投資詐欺とは何か、その手口の特徴や実際の被害事例、そしてだまされないための対策方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。
もし「怪しいかも」と思ったら、この記事で紹介する相談先や対応策をぜひ活用してください。
- SNS型投資詐欺とは
- SNS投資詐欺の手口と被害の実態
- SNS投資詐欺の被害の特徴ときっかけ
- SNS投資詐欺の対策と相談先
- SNS投資詐欺のよくある質問(FAQ)
- 本当に信じてしまう人はいるの?
- お金を振り込んだ後にできることは?
- SNS上で金融庁登録業者を名乗る相手は本当に信頼できますか?
- 少額の投資ならリスクは低いと考えても大丈夫ですか?
- SNSで見かける著名人や芸能人の投資案件紹介は信用できますか?
- 仮想通貨やNFT関連の投資は詐欺が多いと聞きますが、見分け方はありますか?
- 詐欺を疑った場合、どんな証拠を残しておくべきですか?
- 「無料で登録できる」「すぐに始められる」という誘い文句は安全ですか?
- 家族や友人に相談しても軽く受け流されてしまった場合、どうすれば良いですか?
- すでに入金してしまい、相手と連絡が取れない場合はどうすべきですか?
- 「今だけ」「限定募集」などのフレーズは危険ですか?
- 偽物の投資アプリや偽サイトを見分けるポイントはありますか?
- SNS型投資詐欺のまとめ
SNS型投資詐欺とは
「SNS型投資詐欺」とは、SNSやマッチングアプリなどのコミュニケーションツールを使って接触し、巧みに信頼関係を築いた後、偽の投資話で金銭をだまし取る詐欺手口です。
ここではその定義と、混同されやすいロマンス詐欺との違いについて解説します。
SNS型詐欺の定義と仕組み
SNS型投資詐欺は、SNS(LINE、Instagram、Facebookなど)で見知らぬ人物から接触されるところから始まります。
最初は世間話や日常会話などを通じて親しみを持たせ、信頼を築いたうえで、「儲かる投資がある」「特別に教える」などの言葉で投資を勧誘してきます。
多くの場合、詐欺グループは専用のアプリや偽サイトを使い、投資したように見せかけた画面を見せてくるため、被害者は本当に資産が増えていると誤信し、さらなる追加投資をしてしまいます。
最終的には連絡が取れなくなったり、出金できなくなったりして、詐欺だと気づくという流れです。
SNS型ロマンス詐欺との違い
SNS型ロマンス詐欺は、主に恋愛感情を利用して金銭をだまし取る詐欺ですが、投資詐欺と手口が重なる部分も多く、近年ではこの2つを組み合わせた「投資ロマンス詐欺」も増えています。
ロマンス詐欺では、恋人のような関係性を築いたうえで「家族が病気でお金が必要」「海外から帰国する費用がいる」などの理由で送金を求めるケースが一般的ですが、投資詐欺型では「一緒にお金を増やそう」といった形で投資への参加を促してきます。
両者の共通点は、「信頼関係の構築」と「感情への訴え」によって判断力を鈍らせ、金銭を引き出す点です。
手口の複雑化により、詐欺の見分けがより難しくなっているため、警戒が必要です。
SNS投資詐欺の手口と被害の実態
SNS型投資詐欺は、巧妙なコミュニケーションと演出を通じて、被害者に「稼げる」と信じ込ませる詐欺手法です。
ここでは、具体的な勧誘の流れや、実際に報告されている被害事例について解説します。
SNS上での接触から投資勧誘まで
SNS型投資詐欺は、LINEやInstagramなどのSNSで突然のメッセージから始まります。
最初は「間違えて連絡してしまいました」といった自然な接点から会話が始まり、徐々に信頼関係を構築していきます。
ある程度仲良くなったタイミングで、「最近〇〇(仮想通貨、株、FXなど)でうまくいってるんだ」などと投資の話題を持ち出し、専門用語や過去の成功談などを巧みに交えて興味を引きます。
その後、詐欺グループが用意した投資サイトやアプリへ誘導し、最初は少額から始めさせて「儲かった」と感じさせることで、より大きな金額を投資させる仕組みです。
実際の被害事例
警察や報道によれば、SNS型投資詐欺では数百万円から数千万円単位の被害が相次いでいます。
たとえば、徳島県では50代女性が約1,800万円をだまし取られたと報道されており、山口県では女性が約3,100万円を失う被害が確認されています。
徳島県・50代女性が約1,800万円を詐欺被害
NHK徳島(2025年5月8日)
リンク: https://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/20250508/8020022995.html
山口県・女性が約3,100万円を詐欺被害
NHK山口(2025年5月4日)
リンク: https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20250504/4060023041.html
こうした被害は、被害者が最後まで「詐欺だと気づかなかった」ことが多く、見た目には正規の投資に見える精巧なサイトやアプリの存在が被害拡大の要因となっています。
また、「出金したい」と伝えた瞬間に連絡が取れなくなるケースや、追加費用(手数料や税金名目)を要求され続けるケースもあります。
これらの事例は全国各地で発生しており、誰もが被害者になりうる身近なリスクとして認識することが重要です。
SNS投資詐欺の被害の特徴ときっかけ
SNS型投資詐欺の被害者には共通する傾向や心理状態があります。
ここでは、詐欺のターゲットにされやすい層や、詐欺に至るきっかけとなる行動・状況について整理し、読者が自分や家族に当てはまらないかをチェックできるようにします。
よくあるターゲット層
SNS型投資詐欺では、特に以下のような人が狙われやすいとされています。
- 中高年の女性やシニア世代:恋愛感情を利用したロマンス型と併用されやすく、孤独感を抱える人が標的になりやすい。
- 投資初心者:知識が少なく、「簡単に儲かる」といった甘い言葉に引き寄せられやすい。
- お金に不安を感じている層:退職後の資金運用、家計の補填、副業を探している人など。
また、投資に関心がある若年層も標的になるケースがあります。
SNS上での自然な接触により、「自分は詐欺に引っかからない」と思っていた人ほど、冷静な判断を失いやすい点も特徴です。
詐欺に至るきっかけとなる行動
被害者が詐欺に巻き込まれるきっかけには、いくつか共通のパターンがあります。
- SNSでの突然のフレンド申請やメッセージへの返信
⇒軽いやり取りから始まり、親しくなるにつれて投資の話に展開。 - 「実績がある」「他の人も儲かっている」といった言葉への反応
⇒心理的に信頼しやすくなり、リスクを軽視するようになる。 - 少額の投資で実際に利益が出たように見せられる
⇒出金できた、残高が増えたなどの“演出”により本気で信じてしまう。
このように、「ちょっとした返信」や「気軽なやりとり」が詐欺の入り口になっていることが多く、注意喚起と自衛意識の向上が欠かせません。
SNS投資詐欺の対策と相談先
SNS型投資詐欺の被害を防ぐには、日頃からの情報リテラシーの強化と、少しでも不安を感じたときに相談できる窓口の存在が重要です。
このセクションでは、詐欺に遭わないための具体的なチェックポイントと、実際に被害にあった場合の相談先をご紹介します。
詐欺に遭わないためのポイント
SNS型投資詐欺に巻き込まれないためには、以下のようなポイントを意識することが大切です。
- SNSでの見知らぬ人物からの連絡には安易に応じない
→ 特に「間違えました」「投資に興味ありますか?」などのメッセージには要注意。 - 「必ず儲かる」「損しない」などの表現を信じない
→ 投資に絶対はありません。過去の実績や他人の成功談は演出の可能性があります。 - 出金できるか確認するまでは追加投資をしない
→ 利益が増えても、実際に出金できなければ意味がありません。 - 正規の金融業者かどうかを金融庁の登録情報で確認する
→ 金融庁の「登録業者リスト」などで確認可能です。 - 不自然な日本語や外国人名、豪華すぎるプロフィールには要注意
→ 多くの詐欺アカウントは翻訳文や過剰な演出を伴っています。
一見、親切で丁寧な対応に見えても、相手の目的は金銭を引き出すことです。
「おかしい」と思ったら、家族や専門機関に相談するようにしましょう。
相談窓口と通報先
もしも「詐欺かもしれない」と感じたら、以下の機関に早めに相談しましょう。早期対応が被害の最小化につながります。
- 消費者ホットライン(188)
最寄りの消費生活センターにつながります。土日も対応している地域があります。 - 警察相談専用電話(#9110)
詐欺に関する相談を受け付けています。緊急性がある場合は110番通報を。 - 各都道府県警察の特殊詐欺対策ページ
多くの警察署が最新の詐欺情報や相談窓口を掲載しています。たとえば以下のようなページがあります: - 国民生活センターのWebフォームやLINE相談窓口
近年はLINEでの相談も受け付けており、気軽に相談できる環境が整っています。
詐欺は「相談しても無駄」と思い込んでしまうことで被害が拡大しがちです。「念のため確認したい」という気持ちでも、相談することが最善の一手になります。
SNS投資詐欺のよくある質問(FAQ)
本当に信じてしまう人はいるの?
はい、多くの人が実際に信じてしまい、被害に遭っています。
SNS型投資詐欺は、いきなりお金を要求するのではなく、長期間にわたって信頼関係を築くように設計されています。
「仲良くなった人が嘘をつくはずがない」「過去に出金もできたし、大丈夫」といった心理状態に追い込まれ、冷静な判断ができなくなるのが特徴です。
専門知識の有無に関わらず、誰でも騙される可能性があるため、「自分は大丈夫」と思わずに、少しでも違和感を感じたら周囲に相談することが大切です。
お金を振り込んだ後にできることは?
まずはすぐに警察(#9110)または消費生活センター(188)に相談してください。
振り込んだ金融機関に連絡し、振り込みの停止措置を依頼することも重要です。
被害届を出せば、場合によっては「振り込め詐欺救済法」に基づき、資金を取り戻せる可能性があります。ただし、対応が遅れるほど返金の可能性は下がります。
また、今後同様の被害に遭わないためにも、詐欺の手口や防止策について学び、家族や周囲にも共有することが効果的です。
泣き寝入りせず、必ず何らかの行動を起こすことが、被害拡大を防ぐ第一歩となります。
SNS上で金融庁登録業者を名乗る相手は本当に信頼できますか?
金融庁に登録されていること自体は確認すべきポイントですが、登録をかたる偽業者も多いため注意が必要です。
必ず金融庁の公式サイトで業者名・登録番号を確認し、連絡先や所在地などが一致するかを確認しましょう。
少額の投資ならリスクは低いと考えても大丈夫ですか?
少額でも安心とは言えません。
詐欺では「小額で成功体験を与えてから大きな投資を促す」手口が多く、次第に被害額が拡大するケースがよく見られます。
SNSで見かける著名人や芸能人の投資案件紹介は信用できますか?
著名人の名前や写真を無断で使用しているケースがあり、信頼の根拠にはなりません。
必ず公式アカウントかどうかを確認し、本人が正式に関与している証拠がなければ注意が必要です。
仮想通貨やNFT関連の投資は詐欺が多いと聞きますが、見分け方はありますか?
運営者の素性が不明瞭、利益を保証する文言が多用されている、公式な取引所で取り扱われていない、といった特徴があれば危険信号です。
透明性と第三者の評価を必ず確認しましょう。
詐欺を疑った場合、どんな証拠を残しておくべきですか?
SNSのメッセージ履歴、入出金明細、サイトやアプリのスクリーンショットなどを保存しておきましょう。
相談窓口や警察に被害を届け出る際の重要な資料になります。
「無料で登録できる」「すぐに始められる」という誘い文句は安全ですか?
無料登録をうたっていても、その後「出金手数料」「税金」などの名目で高額を請求されることがあります。
簡単に始められることを強調する案件ほど慎重に確認しましょう。
家族や友人に相談しても軽く受け流されてしまった場合、どうすれば良いですか?
周囲が深刻に受け止めてくれなくても、消費生活センターや警察の相談窓口など公的機関に相談することをおすすめします。
専門的な視点で対応してもらえるため安心です。
すでに入金してしまい、相手と連絡が取れない場合はどうすべきですか?
銀行や決済事業者にすぐ連絡し、送金停止や返金の可能性を確認しましょう。
同時に警察や弁護士にも相談して、被害届や法的対応を進めることが大切です。
「今だけ」「限定募集」などのフレーズは危険ですか?
はい。人の心理を利用して冷静な判断を鈍らせる典型的な手口です。
焦らせる言葉が使われているときは特に注意が必要です。
偽物の投資アプリや偽サイトを見分けるポイントはありますか?
公式サイトに似せたドメイン名やアプリ名を使うことが多いです。
配布元や運営会社情報を確認し、アプリストアのレビューや過去の利用者の評判も必ずチェックしてください。
SNS型投資詐欺のまとめ
SNS型投資詐欺は、誰もが使うSNSやアプリを舞台に、信頼関係や感情に巧みに入り込んでくる新手の詐欺です。
特に「簡単に儲かる」「あなただけに教える」といった甘い言葉には注意が必要で、被害は年齢や知識に関係なく広がっています。
本記事では、詐欺の基本的な仕組みから実際の被害事例、そして予防策や相談先まで詳しくご紹介しました。
大切なのは、「もしかして…」と思ったその直感を信じて、一人で抱え込まずに誰かに相談することです。
自分自身や大切な人を守るためにも、この記事の内容をぜひ周囲にも共有してください。
そして、日々変化する詐欺の手口に対し、正しい知識と冷静な判断力を持ち続けましょう。


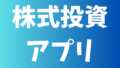
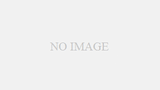
コメント